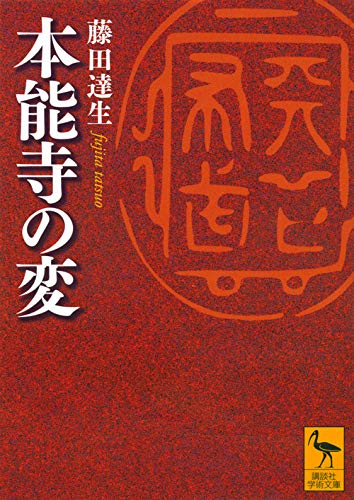2019年35冊目の読書レポートは、『安楽死を遂げた日本人』(著 宮下洋一/小学館 初版2019年6月10日)。書店で目にして手に取りました。
著者はスペインを拠点に活動するジャーナリスト。欧米各国の安楽死事情を取材して上梓した『安楽死を遂げるまで』は、第40回講談社ノンフィクション賞を受賞しています。
本書はその続編ともいうべきもの。5万人に1人が発症するという神経性の難病「多系統萎縮症」を患い、スイスで安楽死を遂げた女性(小島ミナさん)、末期がんに侵され安楽死を望みながら亡くなった男性、末期がんであることを公表し安楽死を望んでいる写真家の幡野広志さんなどを取材してまとめた「安楽死」をめぐるルポルタージュです。
先月放送されたNHKのTV番組『彼女は安楽死を選んだ』では、小島さんが安楽死する衝撃的ともいえるシーンが映し出され、大きな反響を呼びました。著者はコーディネーターとして番組制作にも関わっていますが、その経緯は、本書で明らかにされています。
本書でも、小島さんとその家族(姉妹)が物語の中心。小島さんの生い立ち、病気が判明してからの闘病の日々、家族の献身的な介護、自殺未遂を経て募る安楽死への思いと葛藤、そして困難に次々に遭遇しながらも、スイスへ旅立ち安楽死を遂げるまでの様子が、克明に綴られています。
ところで、薬物の服用または投与による「積極的安楽死」を認めている国は限られており、もちろん日本では認められていません。また本書によれば、緩和ケア技術の進むイギリスでは、安楽死を認めている国々を緩和ケア後進国と見なしているとのこと。「積極的安楽死」への批判は根強いものがあります。
緩和ケアというと、日本では終末期医療のイメージがありますが、広くは「治癒が難しい進行性の疾患で病期によらず苦痛の緩和を目指す医療やケアのこと」を指すそうです。そうすると、小島さんのような難病患者にも緩和ケアは有効なのかもしれません。
しかし、身体機能が次第に失われ、やがて四肢が動かなくなって寝たきりとなり、言葉も話せなくなる。しかも、先が見通せないというような極限状態に置かれたとき、人それぞれ考えることは違うはずです。
「今、命が終わることに悔いはありませんし、抵抗も感じません。命は有限ですから、いつかは終わりの時をむかえます。しかし、機能を殆ど失くし、人工呼吸器で息をし、話すことも出来ず、胃瘻で栄養を身体に送り込み、決まった時間にオムツを取り換えて貰い、そうやって毎日を過ごしたくはないのです。そうまでして、生きる必要性を私自身感じません。寝たきりになる前に自分の人生を閉じることを願います。」
「死にたくても、死ねない私にとって、安楽死は、“お守り”のようなものです。安楽死は私に残された最後の希望の光なんです」
「…私のような状態になった人間にあなたはどんな言葉をかけますか?『がんばって生きて』とも『死んでくれ』とも言えないでしょう。かける言葉がないと思うんです。そういう人間がどう生きればいいのか。世の中の病気でない人たちにも、少しでも考えてもらえるようになればと思います」…。
小島さんの言葉は深く、重いものがあり、胸に迫ってきます。小島さんの信念ともいうべきものに、返す言葉は見つかりません。
そして小島さんが安楽死を遂げる場面では、小島さんの家族への思いと、家族の小島さんへの思いが交差し、読んでいて涙が止まりませんでした。
それは安楽死に至るまでにそれぞれが抱いた苦悩や葛藤を、多少なりとも共有したからかもしれません。小島さんと家族の姿を知ると、「安楽死は間違っている」と簡単には言えなくなってきます。
もちろん、小島さんの安楽死は、小島さんとその家族だからできたこと。たとえ小島さんと同じ境遇になったとしても、安楽死の選択がいつも正しいとは限らないでしょう。小島さんも、自分の安楽死が「良き例」になることは望んではいません。
それでも、「他者の迷惑になりたくない」という日本人的な考えではなく、人間として自らの尊厳を守るために、自分の意志で安楽死することが、本当にいけないことなのか。自分が小島さんだったらどうするのか。小島さんの問いかけは心を揺さぶり、死のあり方、生きることの意味について考え込んでしまいました。
著者は安楽死を肯定的には見ていません。しかし、小島さんの死に立ち会い、まだ懸念は消えないものの、安楽死に対する考え方に変化があったようです。小島さんの遺したものの大きさを物語っています。
「日本における安楽死の問題に一石を投じてほしい。ペンの力でみんなを啓蒙してほしい」。本書が小島さんの願いを叶えたことは間違いないでしょう。
小島さんのご冥福をお祈りします。